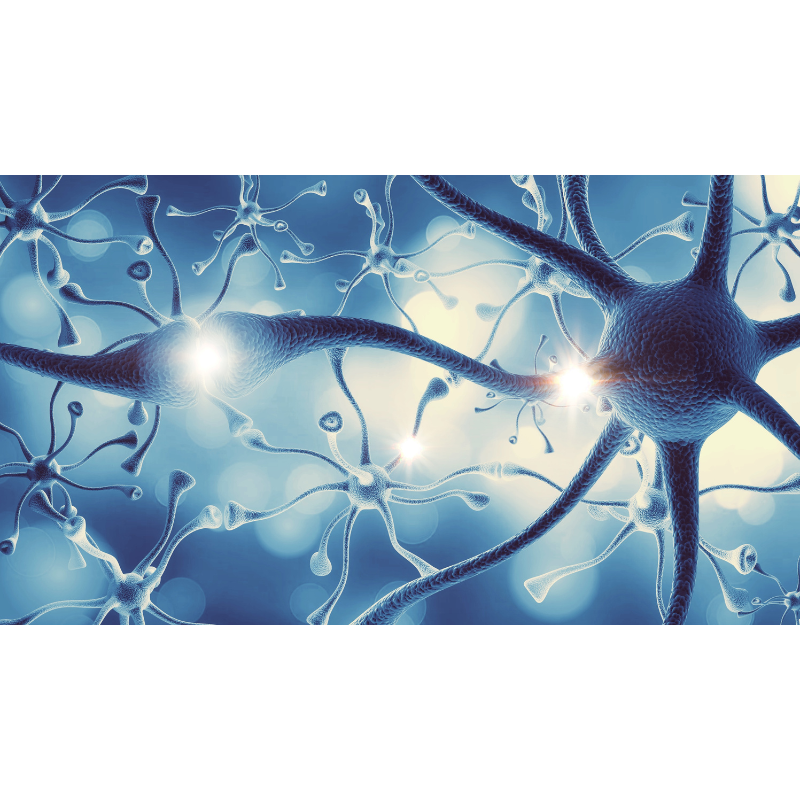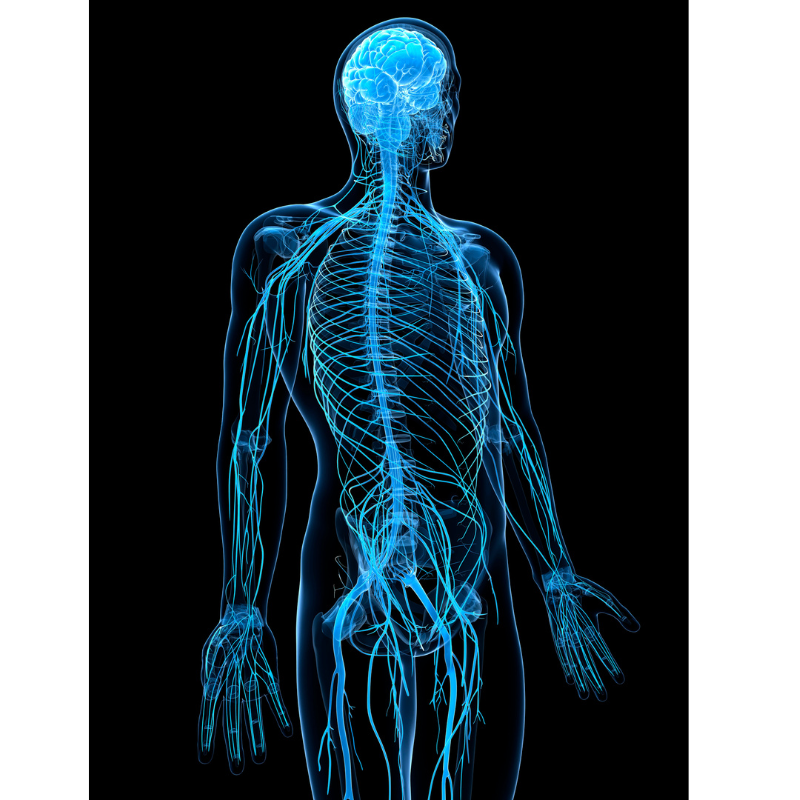交通事故に遭ってしまったとき、ケガの治療や車の修理、仕事への影響など、多くの負担がかかります。そのような被害に対して「慰謝料」を請求することができますが、実はただ待っているだけでは十分な額を受け取れないことも少なくありません。
交通事故に遭ってしまったとき、ケガの治療や車の修理、仕事への影響など、多くの負担がかかります。そのような被害に対して「慰謝料」を請求することができますが、実はただ待っているだけでは十分な額を受け取れないことも少なくありません。
今回は、交通事故後に適正な慰謝料をもらうためのコツを5つのポイントに絞って解説します。事故後の対応に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
1. 医師の診断書をしっかりもらい、通院記録を残す
慰謝料は、ケガの程度や通院日数に大きく影響を受けます。そのため、事故後は必ず医師の診断を受け、診断書を取得しましょう。たとえ痛みが軽微であっても、後から症状が悪化するケースは多く、早めの受診が重要です。
また、通院は「継続性」が重視されます。数日おきに間隔が空いてしまうと「治療の必要性がない」と判断され、慰謝料が減額される恐れがあります。なるべく継続的・定期的に通院することが、適正な慰謝料を受け取るポイントです。
2. 相手側保険会社の提案を鵜呑みにしない
 事故後、加害者側の保険会社から慰謝料の提示をされることがありますが、その金額が「適正」とは限りません。保険会社はなるべく支払額を抑えたい立場にあるため、最低限の基準(自賠責基準)で計算していることがほとんどです。
事故後、加害者側の保険会社から慰謝料の提示をされることがありますが、その金額が「適正」とは限りません。保険会社はなるべく支払額を抑えたい立場にあるため、最低限の基準(自賠責基準)で計算していることがほとんどです。
実際には「弁護士基準(裁判基準)」で請求することで、数十万円〜場合によっては100万円以上の差額が出ることもあります。示談の前に、相場や基準について調べることが大切です。
3. 示談書にサインする前に専門家へ相談する
 保険会社との示談交渉では、一度サインをしてしまうと、その後に内容を変更することはほぼ不可能になります。「とりあえずサインしてしまったが、後から痛みが残った」「もっと請求できたと知った」などの後悔を避けるために、示談書には慎重になるべきです。
保険会社との示談交渉では、一度サインをしてしまうと、その後に内容を変更することはほぼ不可能になります。「とりあえずサインしてしまったが、後から痛みが残った」「もっと請求できたと知った」などの後悔を避けるために、示談書には慎重になるべきです。
もし内容に不安がある場合は、交通事故に強い弁護士や行政書士、あるいは自分の加入している保険会社の「弁護士特約」を活用して、専門家に確認してもらいましょう。
4. 写真や記録を残すことも忘れずに
 事故の状況やケガの様子、通院時の診療明細や領収書など、客観的な証拠を残すことは慰謝料請求において非常に重要です。特に、事故現場の写真や車両の損傷状況は、後で事故の重大さを証明する材料になります。
事故の状況やケガの様子、通院時の診療明細や領収書など、客観的な証拠を残すことは慰謝料請求において非常に重要です。特に、事故現場の写真や車両の損傷状況は、後で事故の重大さを証明する材料になります。
また、日記のように痛みの推移や通院の様子をメモしておくことも、後のトラブル時に役立つケースがあります。証拠は多ければ多いほど、あなたの主張を裏付ける材料になります。
5. 弁護士に依頼することで慰謝料は大きく変わる
 特に重度のケガや後遺症が残った場合、弁護士を通じて慰謝料を請求することで、金額が大きく変わる可能性があります。保険会社と直接交渉するよりも、法律の専門家が入ることで「弁護士基準」での請求が可能となり、正当な額を主張できるようになります。
特に重度のケガや後遺症が残った場合、弁護士を通じて慰謝料を請求することで、金額が大きく変わる可能性があります。保険会社と直接交渉するよりも、法律の専門家が入ることで「弁護士基準」での請求が可能となり、正当な額を主張できるようになります。
また、「弁護士費用特約」に加入していれば、自己負担なしで弁護士を利用することも可能です。この特約があるかどうか、自分の保険証券を確認しておくと良いでしょう。
まとめ
慰謝料は「知っているか」で大きく変わる
交通事故に遭った直後は、精神的にも身体的にも大きなダメージを受けている状態です。しかし、そこで適切な対応をしないと、本来受け取れるはずの慰謝料を大きく損してしまうこともあります。
慰謝料をもらうための5つのコツまとめ
- 早めに医師にかかり、通院記録を残す
- 保険会社の提示をうのみにしない
- 示談前に専門家へ相談する
- 写真や診療明細など証拠をしっかり残す
- 必要に応じて弁護士に依頼する
大切なのは、泣き寝入りせず「正当な権利」を主張することです。事故の被害者だからこそ、しっかりと情報を集め、納得のいく補償を受け取りましょう。
東洋スポーツパレス鍼灸整骨院
急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!
交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する
📞092-852-4551
〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40
病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、交通事故に関わるどのよう内容でも相談無料にてお受けいたします。
交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。